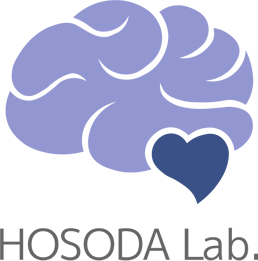Child Care Commonsの活動メンバー
家族や地域を社会学の視点から研究しています。日本は子育てに喜びを感じにくい社会であるということが指摘され、様々な政策的取り組みがなされて久しいですが、大きな変化は生じていないように見えます。こうした状況を変えていくためにも、新しい視点が求められています。私の現在の研究では、それぞれの地域が置かれた特徴や実情に寄り添いながら、子育てを社会に開いていくための具体的方法を検討するための実態調査に取り組んでいます。
皆さんは、ストレスを感じたとき、胸がどきどきしたり、眠れなくなったり、食欲がなくなったり(逆に増したり)した経験はありませんか。私たちのチームでは、お子さんたちが日々どんなことにストレスを感じ、どのように体の反応として表れるのかを、心電図、睡眠の質、食事、髪の毛の中の“ストレスホルモン”の量など、いろいろな角度から調査します。また、そんな体の反応が、自分を支えてくれる人々との出会いや、日々の出来事の中でどう変わっていくのかについても研究し、子どもたちが幸せに生きるために何ができるのか、皆さんと一緒に考えていきます。
子どもが夢や希望を持ち、自分らしく生きていくためには、信頼できる人とのつながり(ソーシャルキャピタル)が大切です。この研究では、被災地をふくむ地域で、学校・家庭・地域との関係を調べ、子ども一人ひとりが安心して育つ教育を含む環境のあり方を考えます。子どもの心の元気(心理的資本)を育てるために、社会全体がどのように支えられるかを探る取り組みです。
芸術介入によって子どもの社会適応を促す介入法の確立を目指し、「①個別最適化された芸術活動の開発」「②社会実装のための基盤づくり」に関する研究を進めます。創作や鑑賞といった多様な芸術活動の効果を、子どもの個性や参加形態に応じて科学的に評価し、その有効性を検証します。また、地域における芸術活動の提供手段としてアウトリーチのあり方を検討し、支援の届きにくい子どもたちへの介入を通じて、社会的つながりの形成とその持続可能性の解明を目指します。
子どもと養育者との関係性を客観的指標に基づいて定量化することを目指します。具体的には、親に対する質問紙調査だけでなく、子どもと親の両者を対象とした実験室実験・オンライン実験パラダイムを構築することで、長期縦断的な視点から社会関係資本の在り方を探ります。
本研究課題では、第三者含む子育ちに関わる協働体においてSNS等で行われるコミュニケーションから、協働体の人々のプライバシーを守りながら、社会関係性を可視化し、その関わりを証明・開示するシステムに関する研究開発を行います。また、協働体の人々がウェルビーイングに関わるためのプロセスをウェルビーイング促進の国際標準ISO25554に基づいて検討します。
子どもが必要な支援や教育を受けたり、自尊感情や自立性を高めるためには、社会関係資本を適切に可視化し、それを周囲に積極的に発信するアプローチが有力です。本研究では、センシング技術・情報提示技術を応用し、コミュニケーションの種類や頻度を可視化して共有し、同期性や類似性情報を明らかにすることで、子どもに対する有効な支援につなげます。
現代の社会では、生活スタイルの多様化によって家族や地域のつながりが弱くなり、子どもが孤立してしまうことがあります。本研究では子どもが自信や将来の希望をもって成長できるよう、家族や地域の人々や他の子どもたちと協力しながら学び続けていくための仕組みを考えます。家庭環境や地域の違いを乗り越えることを目指し、まずは離島や過疎地域を対象にオンラインを活用しながら、全国に展開できる教育プログラムを開発します。
第三者が親子に関わることで、どのようなことが起こるのでしょうか。おやまちリビングラボで実際に「チーム家族」の実践を長期的に行い、その効果や課題を明らかにし、関係が持続するための介入や支援の仕組みづくりを検討します。また、実践によって得られた知見にもとづいて体験ツールやワークショップを設計し、企業や地域NPOを通じて社会的認知を広げ、CCCの関係性を広げていく可能性を探ります。